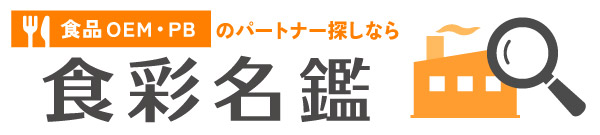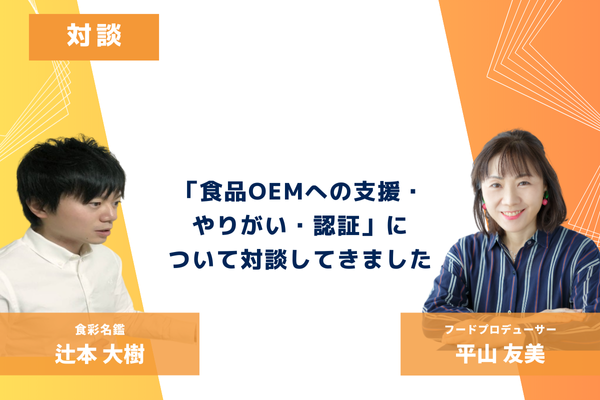こんにちは。
食品OEM・PBポータルサイト「食彩名鑑」です。
先日、「食」を核とした企画開発を得意とするフードプロデューサーの平山さんに「食品OEMへの支援・やりがい・認証」について対談させて頂きました。今回は、その対談内容をブログ記事にまとめてみました。
「OEM支援の実例を知りたい。」「食品業界の認証(HACCP、FSSC22000 etc)の必要性を知りたい。」「食品企業への支援のやりがいを知りたい。」という方向けになります。
お話ししてすごく楽しかったです^^よかったらご覧ください。
コラボ対談者(登場人物)
 辻本
辻本東京農業大学卒業後、食品メーカーに入社。食品系オウンドメディアを複数運営しながら法人様に業務改善・集客支援を行っています。食品メーカーの営業マン時代、OEM生産・PB商品化に携わっていた経験から「食彩名鑑」を立ち上げました。
資格:惣菜管理士資格試験 1級取得・食品表示検定 中級 取得
食事業と経営の架け橋になるフードプロデューサーのお仕事とは?



本日はよろしくお願いします。



よろしくお願いします。



平山さん、簡単に自己紹介をお願いできますか?



平山友美と申します。私はフードプロデューサーという肩書で、食に関する仕事を専門に行っています。



ありがとうございます。
フードプロデューサーというのは、具体的にはどのようなお仕事ですか?



深く説明すると長くなりますが、食に関する仕事というと、多くの人が「料理の先生ですか?」とか「フードコーディネーターですか?」と聞かれます。フードコーディネーターや料理家はイメージがしやすいと思いますが、フードプロデューサーはその両方の役割ができるだけでなく、事業の相談に乗る点が大きな違いです。



はい。



フードコーディネーターも撮影などで商品に触れる機会が多いので、事業者様や企業様との接点は多いです。ただ、販促物を作る場合だと営業担当者や他の担当者が間に入っていることが多いと思います。一方で、フードプロデューサーの場合は、まず経営者様と直接話をしなければ始まらないんです。経営の相談ではありませんが、経営者様と話し合いながら、どのような商品を作り、どこに売るかといった戦略から一緒に考えるのが特徴的な仕事です。



ありがとうございます。もともとプロデュースのお仕事をされていたんですか?



いえいえ、フードプロデューサーは、いきなり目指せる職業ではありません。料理の仕事やフードコーディネーターの経験をしっかり積んだ上でなる職業です。
OEM支援事例と業務の楽しさ・難しさ



そうなんですね。プロデューサーとして、食品のOEMに関する支援のご経験はありますか?



はい、あります。



具体的にどのようなことをされているか、可能な範囲で教えていただけますか?



OEMの場合、新規のお客様を獲得するために展示会に出展するケースが多いんです。例えば、スーパーマーケットトレードショーやフーデックスがよく知られています。私は、出展される際のブースについてアドバイスをしたり、新規のお客様にお渡しするパンフレットや会社案内、OEM受注の流れなどを説明する資料を作成したりしています。



そうなんですね。OEM支援をしていて難しいと思うことはありますか?



同じ「お客様」という言葉を使っても、OEMを依頼する企業と商品を購入する消費者は、全く違うということを意識しないといけないですね。OEMのお客様に魅力的に伝えることと、消費者に対して魅力的に見せることでは、使う言葉や見せ方が全く違います。その違いを踏まえて、どう伝えるのかを考えることが楽しいところであり、難しいところでもあります。



確かに。そうですよね。
食品業界の認証(HACCP、FSSC22000 etc)の必要性



食品のOEMであれば、特に、HACCPやFSSC22000といった認証も必要になってくるかと思いますが、平山さん、どのようにお考えですか?



はい、OEMを受託したいと考えている企業さんなら絶対に取得しておいた方が良いです。



ただ、それらは消費者にはあまり馴染みがないですよね。



そうなんです。消費者にとっては「すごいことなのかどうか」もわからないですよね。工場で働く方にとっても、「なんだこれは?」と感じることがあるかもしれません。ただ、単にマニュアルが増えただけのように思われると、本質的な変化が起きません。「安心で安全な商品をお客様に届ける」という意識を共有し、社内全体で取り組むことが大切です。そうでなければ、認証取得が単なる目的になり、コンサルタントが来る時だけ対応するといった状態になってしまいます。



そうですね。



OEMを受託したい企業にとって、認証を取得しているだけでは強みになりません。ただし、そのプロセスでどのような取り組みを行ったかを話せると、取引先に魅力的に伝えられます。それが差別化にもつながります。



認証の取得が目的ではなく、手段ですよね。もともとはフードディフェンス(食品防御)や異物混入対策のために必要とされる資格です。OEMを依頼する側もされる側も、慎重になる部分ですよね。



はい。規模が大きい企業がOEMを受ける場合、当然、信頼性の高いHACCP認証を取得していて、工場の設備も整っていますよね。でも中小企業がOEMを依頼する場合「大量にはいらない」と考えます。食品には賞味期限がありますから、あまり大量に作っても売り切れなかったときロスになります。だから「小ロットから対応してもらえますか?」という要望が多いんです。そういった小ロットに対応できる工場が信頼性の高いHACCP認証を取得していると、非常に大きな強みになります。



はい。



「規模が小さいから認証を持っていないのは仕方がない」という考え方は、今の時代には通用しません。認証にも色々ありますし、規模が小さいからこそ、社員全員が安全意識を高く持ちながら、ものづくりをしていくことが重要だと思います。機械が古くても、安全管理がしっかりできているということが第三者機関によって証明されることが大事だと感じます。



おっしゃる通りで、どこの認証もないと取引を開始してもらえなかったり、取引口座を開いてもらえない会社もあります。



そうですよね。第三者機関に認めてもらえるという点が大きいですよね。
認証を取る前は大手のお取引先から毎月のように監査が入って、それが大きなプレッシャーになっていた。しかし、認証を取得した途端に、その監査が緩和されたというケースはよくあります。



はい。サラリーマン時代、監査の営業対応には苦労した覚えがあります。工場の方もピリピリしていました。また、認証があることで監査が少し楽になる場合もありますが、それでも監査自体は依然として厳しいものです。
食品企業への支援のやりがい



食品企業に対して様々な支援をされてきたと思いますが、これまでの中で特に「やっていてよかった」と実感したことはありますか?



私は会社法人という形ではありますが、一人で活動しています。そのため、どの会社様とお仕事をしても「よそ者」なんですよ。でも、そんな私に相談をしてくださり、提案したことが形になって、展示会のブースや販促物が完成する。そして、それが役立って商談が決まったり、展示会の反応が良かったという結果を一緒に喜べる瞬間が、私にとってはとてもやりがいを感じるところです。社員の一員のように受け入れていただき、一緒に成果を喜べる場を与えてもらえるのは、本当にありがたいですね。



わかります。私もサラリーマン時代に加工食品のOEMやPBに携わっていましたし、独立後は紅茶やハーブティなどの商品化を支援しました。やはり商品が形になる瞬間には特別な喜びがありますね。調整は大変ですが、完成した時の達成感やもっと多くの人に売れたらいいなと思う気持ちは共感します。
地域の食文化を支え、未来を築く!フードプロデューサーとして挑む課題とビジョン



フードプロデューサーとしてご活躍されていますが、今後目指していきたい未来についてお聞かせいただけますか?



私は今、広島を拠点にプロデューサーとして活動しており、その名に恥じないような仕事を心がけています。先ほどもお話しましたが、私はこの仕事に大きなやりがいを感じています。特に、顔の見えるお客様に喜んでいただけているという手応えを感じられることが大きいです。



はい。



以前は専業主婦で、そこからいきなり社長になったため、こういった実感を得ることはありませんでした。それを思うと、本当に仕事が楽しいと感じます。この仕事は、自分自身でも長く続けていきたいと思っています。例えば、80歳になっても続けていたいですね。



すごいですね。



同時に、今後は食の仕事に携わりたいと考える方々を全国に増やしていきたいとも思っています。
地方の食品企業は、ほとんど大企業ではありませんよね。フードコーディネーターにとって、名前が知られている大手企業の仕事を実績にしたいと思いがちです。しかし、地元にこそ、自分の活躍できる場所はたくさんあります。



なるほど。



例えば、レシピの提案や少しのお手伝いで売上が上がることも多いんです。地元の食品企業に目を向けて、彼らと関わることを楽しいと感じてくれる人が増えたらいいなと考えています。全国的に名前は知られていなくても、地元で長く愛されている企業を支えることで、もっと多くの人がこの仕事の楽しさややりがいを実感できるようになればと思っています。



良いですね。
関連するご支援も最近されているとお聞きしましたが、いかがですか?



そうですね。講座は始まっているのですが、まだ課題があります。
私の実績を知ってもらい、共感してくださる人を集めようと考えていたのですが、その実績が全国的にはあまり知られていない企業のお仕事ばかりなので、「あの人、知らない会社ばっかりやってる」と思われてしまうのです。



そうなんですね。



私の実績がすごいのに、という意味ではなくて、地元の企業のことが「大してすごくない」と評価されてしまうのではと心配になることがあります。そのため、この仕事自体に興味を持ってもらうのが難しいという課題を感じています。
ただ、この仕事は本当に良い仕事で、やりがいもあるので、引き続き発信を続けていきたいと思っています。
広島発!日常と食を記録する『食の手帳』がつなぐ未来とつながり



最後に、広島に関連する手帳を作られたと伺いました。ぜひお話を聞かせてください。



「ひろしま食の手帖」というご当地スケジュール手帳を出版しました。この手帖はどのページを開いても広島県の食に関する情報に触れられるようになっています。最近では「手帳なんてもう使わないよ」と言われることもありますが、実は手帳の売り上げは若い世代を中心に回復してきています。



はい。



たとえば「推し活」や「ジャーナリング」に利用されていて、日々の出来事を少しずつ書き留める用途が人気です。だらだらと日記を書くのではなく、その日のことを簡単に記録しておくことで、後で振り返る楽しみも生まれます。たとえば、自分の文字を見返して「この日は疲れていたな」「やる気に満ちていたな」と気づくことができ、感情のコントロールにも役立ちます。



なるほど。



また、この食の手帖は食生活の記録にも使えるので、仕事のパフォーマンスややる気とも密接に関連します。生活が整うことで仕事もうまくいくという良いサイクルを作る手助けができると思います。特に女性にとっては、ダイエットや美容の記録にも役立つと思いますね。私自身は、この手帖を食生活の管理に使っています。



はい。



たとえば、水分補給を意識したり、肌の調子を記録したりしています。日々の小さなことでも書き留めておくと、数カ月後にその変化を実感できるのが楽しいです。体重のように数字で表せるものだけでなく、気分ややる気といった感覚的なものも把握しやすくなります。これを続けることで、自分の目標や夢の達成にもつながると思っています。



なるほど。



自分が幸せだと、周りの人に優しく接することができるようになりますよね。



確かにそうですね。



たとえば、子育て中の方であれば、子どもとの関係が良くなり、子どもに優しく接することができるようになると思います。それだけでなく、いろいろな面で良い影響が出てくるんです。この手帳は、今年創刊したばかりなので、これから「食ライフログ」として使っていただき、1年間記録して「やってよかった」と思う人をどんどん増やしていきたいですね。



はい。



また、この手帖は民間のボランティアの方々を中心に作られており、一切広告を入れていません。たとえば、行政が作る冊子だと「農産物」「畜産物」「水産物」といった縦割りで、それぞれの分野しか載っていないことがありますが、この手帖では「広島県民がおすすめしたい食」を横断的にまとめています。肉、野菜、魚だけでなく、加工品やお土産品、さらには居酒屋のメニューまで幅広く掲載しているのが特徴です。毎年内容を変えていく予定で、食を通じたつながりを広げていきたいと思っています。他県の方にもぜひ見ていただきたいですね。



僕も購入させていただきました。カバーも付いていて、ボールペンを挿せるなど実用的ですね。炭水化物やカロリーを記録してみようかと思っています。



とても良いと思います。外食した際のメモを残すとお店の情報を記録できるだけでなく、自分の食生活を見直すきっかけにもなりますね。最近はスマホで写真を撮るだけの方も多いですが、手帖に書いておくことで振り返りやすくなります。



たしかにスマホだと埋もれてしまいますね。



手帖は、記憶を呼び起こす助けにもなります。たとえば、「夏だったよね」「あの子の誕生日会の時だよね」といった情報を手帖から探すことができます。こうした記録があると、思い出を振り返る楽しさも増しますし、人間の脳にも良い影響があります。



確かに手帖ならではの良さですね。



食の手帖の話で熱くなってしまいましたが(笑)



私も愛用させていただいています。本日はどうもありがとうございました。



ありがとうございました。
<関連書籍>


最後に
今回は、「食」を核とした企画開発を得意とするフードプロデューサーの平山さんに「食品OEMへの支援・やりがい・認証」について対談させて頂きました。
僕自身、前職が食品メーカーだったため、すごく良い刺激を受けました。
平山さん、対談して頂きありがとうございました。